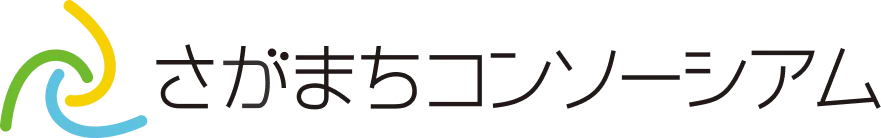市民大学
メニュー
さがまちカレッジ
メニュー
講座詳細
後期対面
はじめての日本の伝統音楽I -雅楽と声明(しょうみょう)
相模女子大学・ 相模女子大学短期大学部
知っているようで知らない日本の伝統音楽文化を学ぶ講座です。伝統音楽に関する基礎知識や音楽的特徴、社会との関わりを知ることで、現在私達が見聞きする伝統音楽や民俗音楽への理解を深めることができます。
今年度は雅楽と声明(仏教音楽)という古代の音楽と音楽を取り巻く文化についてお話しします。第4回では大和市雅楽協会会長をお招きし、みなさんに雅楽の実演をお聞きいただいたり、楽器体験をしていただきます。
開催日時・場所
| 日程 |
① 10月14日(火) ② 10月21日(火) ③ 10月28日(火) ④ 11月11日(火) ⑤ 11月18日(火) |
|---|---|
| 時間 | 10:40~12:10 |
| 場所 | 7号館 712教室 |
講義内容
| ① 10月14日(火) | 日本の伝統音楽概説 |
|---|---|
| ② 10月21日(火) | 雅楽(1)雅楽の歴史、雅楽の曲種 |
| ③ 10月28日(火) | 雅楽(2)雅楽の国風化、雅楽の楽器 |
| ④ 11月11日(火) | 雅楽(3)雅楽を実際に聴く、楽器体験 |
| ⑤ 11月18日(火) | 声明と仏教儀礼 |
詳細
| 講師 |
①~⑤非常勤講師 寺田 真由美 ④ 大和市雅楽協会会長 松永 耕作 |
|---|---|
| 受講料 | 1,300円 |
| 受講料以外の費用 |
500円 楽器使用料として第4回講座受付時に徴収します。お釣りのないように当日現金をご持参ください。 |
| 定員 | 50名 |
| 第4回雅楽の楽器体験について |
●「龍笛」という雅楽の笛や「打ち物」という雅楽の打楽器の体験をしていただく予定です。 ●龍笛は一人一本ずつお貸しし、さらに初めての方でも音が出せるような補助具もお一人ずつお渡ししますので安心してご参加ください。 ●楽器使用料として第4回講座受付時に500円を徴収します。お釣りのないように当日現金でご持参ください。 ●口紅を落として楽器体験を行ってください。 |
| その他 | 車でのご来校はご遠慮ください。 |
アクセス
| 施設名 | 相模女子大学・相模女子大学短期大学部 |
|---|---|
| 住所 | 相模原市南区文京2-1-1 |
| 行き方 | 小田急線 相模大野駅下車 徒歩10分 |